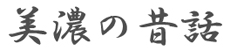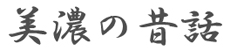| ◆ 仁田四郎由定のこと (櫨原) |
 |
仁田四郎は、門入から戸入へ、山手を経て、ここ櫨原に落人として訪れた。
供の者は無く、ひとり鎧櫃を背に、まず村のとっつきにある(現在早川太七家)後家、おむつの家に足を止め、一夜の宿を求めたのが縁となって、そのままここに逗留した。
見かけは尋常の落人と異って、人品賤しからず、その身装り持ち物等からも、かなり高い身分の侍と見受けられて、事実初対面の当初から、彼には村人全てが一目置いて接した。
ところが或る日、彼の身辺まで、遂に追手の手が延びることとなった。追手は川下の方から併せて三人、四郎逗留の家まで来ると、丁度戸外の水屋で菜を洗っていた主おむつに、しかじかの身の上の者は居るかと尋ねたが、彼女は皆目知らぬと答えた。しかし彼らはその答えに満足せず、おむつの止める手を払って家中に押し入り、(幸いに、四郎は不在であった)そこに不相応の鎧櫃のあるを見届けてしまった。そして討手の数をふやす為にか、その日はその場を一応引き上げた。
さて四郎は、おむつからその日の変事を耳にすると、いよいよ迫った身の危険を避ける為に、翌日村の者へ、次の如き相談をかけた。
もしも自分を主と立ててこの地に築城を許してくれるなら、
一、村上の鬼ヶ平に、私財を投じて地ならしをし、
一、村中に宮谷の水を引き入れて用水並びに堀とする。
そして、今はさる所にて待機している部下を招いてここに住まわせ、村を城下町として栄えさせようではないか。
そこで村人は、よし村一同にてよく協議をし、その上で確かな答えをしようと四郎に伝えて、早速にもその夜集会を開いた。然し集会に於ける衆議のなかみは、四郎にとって思いがけぬものであった。
その夜おむつが密かに伝えた村人の決議というのは、築城などという大事を企てるほど四郎に私財があるのなら、いっそこれを亡き者にして、その私財そっくり村のものにしようではないか、なに、いかに手だれの侍とは言え、あり合わせの武器でこれを押し包めば、打ち取ることも容易、そしてうまくいったら、過日現われた追手の侍どもから、報奨金をせしめることもできるかもしれない、というのである。
築城の話はおいそれとまとまらないにしても、せめて近日中に寄せてくるであろう追手の手から、村こぞって護ってくれる位の事はしてくれるものと信じていた四郎は、事の成り行きの以外さに、かえって悲しみもわかなかった。何という酷い仕打ちを企むものかなと嘆くおむつを逆になだめて、この様な地に至ってもここまで不運であるというのは、四郎の身からことごとく武運が離れ去ってのことである。それと知って自分はかえって落ち着きを得たと述懐した。そして、この村から一刻も早く越前・越中をたよって落ちのびるようにとのおむつの真言も入れず、覚悟の面ざし静かに、討たれる時を待った。
やがて翌日、村人の襲撃より早く追手十数人が、家の周りを囲んで、即座に四郎を討とうとした。が、四郎は果敢にその囲みを破って、追いすがる追手やそれに加わった村人を後目に、神社の森の高杉にかけ登ると、懐中の鳥目(金)七袋半を鷲づかみにして、
「かようなものが、それ程に欲しかったのか!」
と、声高に呼ばわりざま群がる村人の頭上にばら播いた。ところが播かれた鳥目は、地上に落ちるや、そのまま、四くら起き(成長しきった)蚕となって、村の上はずれのしっぺ谷(以後はかいこ谷ともいう)へ這いこんだという。
ついで四郎は、鳥目を播き終えると、今度は、追手の者へ
「子孫の語り草に、四郎最後の姿を見よ」と言いおいて九寸五分なる匕首を尖先からたてにくわえ、まっさかさまにその高杉から飛んで果てた。
さて、四郎の死後、当櫨原村には彼の怨霊が祟りに祟って、先ずはその直後に疫病、次に火災、ことに火災に至っては一度ならず、ふしぎやあの高杉より播かれた鳥目の袋の数に合わせて七回半にも及んだ。火災の直前には必ず、白衣の稚児が、「おおう!」という細い悲しげな声を不吉にふるわせて村中の道を通り、その稚児が村上から村下に向かえば火の手もまたそれを追うように上から下へ、稚児が下から上に向かえば火もそのようにと燃え拡がっていったという。
然し四郎をかくまい通した後家おむつの家だけは、重なるその火災ごとに、軒の外柱を焦がすのみで類焼を免れた。その類焼を免れたおむつの家の柱だというものが、昭和の時代に至るまで残っていて、人々を不思議がらせた。(また、不思議と言えば、四郎が脱れた神社の高杉の辺り一帯には、あたかも蚕の糞と思われる異状の黒い土粒が確かに在って、話に興を添えている。)
村人は個の怨霊の祟りに心底から怯えおそれ、それから四郎自害の、五月二十八日を期して、この霊を祭った。現在残っている自然石の墓標の面には、仁田四郎由定之墓と刻んであるが、これはあくまで、彼が勤皇の士であったこと、また彼が祭られている藤島神社が官幣大社にまで昇格していたことなどから、地元の者たちが国の目をおそれて、故意にその実名を用いなかったまでのことで、実はこの四郎なる侍は、新田四郎義貞公であったと伝えられている。
たとえば、かなり後世になって、この村を訪れた一巡礼が、墓じるしの五輪に刻まれた四郎の履歴を一読するや、我が君様は、かくなる所で果てられたかと嘆き悲しんで後、それをそのまま持ち去ってしまったとか、或いは又それより更に後、岐阜地区に住む某とかいう仁が、所持して居る貞義公直筆の文書中に、ここ岐阜地区まで出て来てみたが、世は未だ治まらず物騒であるので、再び美濃の徳山までひき返すことにすると書いてあったと語って、この地を訪れたことがあるとか、彼四郎が実の義貞公であるに相違ないという説は、当地では今も専らである。
編集発行は徳山小学校 昭和45年の発行
櫨原は徳山村の地域の名前です
|
|
|